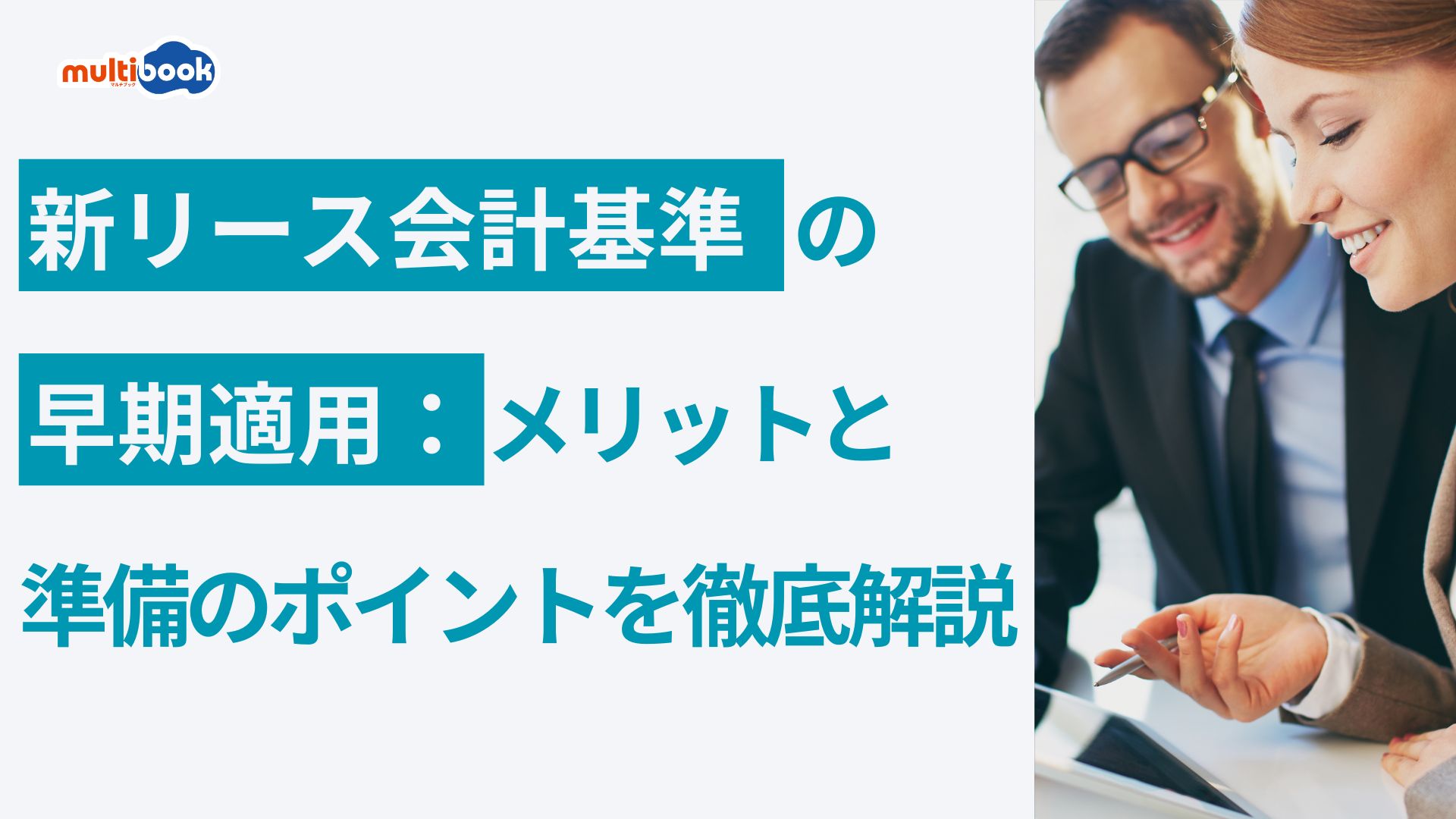はじめに: 新リース会計基準の概要と早期適用の重要性
企業の会計実務に大きな変革をもたらす新リース会計基準が、いよいよ適用開始の時期を迎えようとしています。この新基準は、特にオペレーティング・リースやレンタル契約における借手側の会計処理に重要な変更をもたらし、多くの企業の財務諸表に大きな影響を与えることが予想されます。
新リース会計基準の最大の特徴は、これまでオフバランスだった多くのリース取引をオンバランス化することです。これにより、企業の資産と負債が増加し、財務指標に大きな変化が生じる可能性があります。このような変更に対応するためには、十分な準備期間が必要となります。
そこで注目されているのが、新リース会計基準の早期適用です。本記事では、新リース会計基準の早期適用に関する重要なポイントを解説し、企業がどのように準備を進めるべきかについて詳しく説明します。
新リース適用準備の重要ポイントがまるわかり!「完全ガイドブック」のダウンロードはこちらから>>
目次
新リース会計基準の適用時期と早期適用(任意)
新リース会計基準の適用開始時期は、連結財務諸表と単体財務諸表の両方において、2027年4月1日以後に開始する事業年度からとなっています。しかし、企業によっては2025年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用することも可能です。
この早期適用の選択肢は、企業に準備のための時間的余裕を与えると同時に、新基準への移行をスムーズに行うチャンスを提供しています。しかし、早期適用を選択するかどうかは、各企業の状況や戦略によって慎重に判断する必要があります。
早期適用のメリットとデメリット
新リース会計基準の早期適用には、いくつかのメリットとデメリットがあります。これらを十分に理解し、自社の状況に照らし合わせて検討することが重要です。
メリット
- 準備期間の確保:
早期適用を選択することで、新基準への対応に十分な時間をかけることができます。システムの整備や業務プロセスの見直しなど、必要な準備を余裕を持って進められます。 - 先行者利益:
業界内でいち早く新基準に対応することで、投資家や取引先からの評価が高まる可能性があります。また、同業他社に先駆けて経験を積むことができます。 - 段階的な移行:
早期適用期間中に発生した問題点を洗い出し、本格適用までに改善することができます。これにより、スムーズな移行が可能になります。 - 財務諸表の比較可能性向上:
IFRSを採用している企業や海外子会社との財務諸表の比較可能性が向上します。これは、グローバルに事業を展開している企業にとって特に重要なメリットとなります。
デメリット
- 初期コストの発生:
システム改修や人材教育など、早期に対応するための初期コストが発生します。 - 業務負担の増加:
新基準への対応に伴い、一時的に業務負担が増加する可能性があります。 - 比較可能性の一時的な低下:
同業他社が新基準を適用していない場合、財務諸表の比較可能性が一時的に低下する可能性があります。 - 不確実性への対応:
税務上の取り扱いなど、まだ明確になっていない部分への対応が必要となる可能性があります。
新リース会計基準に完全対応!multibookリース資産管理システムのサービス紹介資料をメールで受け取る>>
早期適用に適した企業のケース
新リース会計基準の早期適用が特に有効と考えられる企業のケースをいくつか紹介します。
- IFRSを採用している企業:
連結財務諸表でIFRSを適用しており、単体財務諸表にもIFRSの会計処理を反映するためのインフラやフローを構築済みの企業は、早期適用のメリットが大きいでしょう。 - 海外子会社が多い企業:
海外子会社の多くがIFRSまたはそれに近い会計基準を採用している場合、早期適用によってグループ全体の会計処理の統一が図れます。 - リース取引の少ない企業:
国内でのリース取引が少なく、新基準の影響が限定的な企業は、比較的スムーズに早期適用を行える可能性があります。 - 既存のリース管理システムが充実している企業:
現行のファイナンス・リースの管理に適したシステムを導入済みの企業は、新基準への対応がしやすい可能性があります。 - 近い将来にIFRS移行を予定している企業:
IFRSへの移行を計画している企業にとって、新リース会計基準の早期適用は良い準備となるでしょう。
新リース会計基準導入に向けた準備ステップ
新リース会計基準の導入に向けて、以下のようなステップで準備を進めることをお勧めします。
- 影響度の評価:
自社のリース取引の棚卸しを行い、新基準適用による財務諸表への影響を試算します。 - プロジェクトチームの結成:
経理部門だけでなく、IT部門や各事業部門を含めたプロジェクトチームを結成し、全社的な取り組みとして準備を進めます。 - システム対応の検討:
新基準に対応したリース管理システムの導入や既存システムの改修を検討します。 - 業務プロセスの見直し:
リース契約の管理から会計処理、開示資料の作成まで、関連する業務プロセスを見直し、必要に応じて再構築します。 - 社内規程の整備:
新基準に基づいた会計方針や社内規程を整備します。 - 教育・トレーニング:
関係部署の担当者に対して、新基準の内容や新しい業務プロセスに関する教育・トレーニングを実施します。 - 移行方法の決定:
完全遡及アプローチか修正遡及アプローチかを検討し、最適な移行方法を決定します。 - 開示情報の準備:
新基準適用に伴う注記事項の増加に対応するため、必要な情報の収集・集計方法を確立します。
新リース適用準備の重要ポイントがまるわかり!「完全ガイドブック」のダウンロードはこちらから>>
システム対応の重要性
新リース会計基準の適用に伴い、企業は会計処理の方法を根本的に見直す必要があります。この新基準では、すべてのリース取引がオンバランス化されるため、企業の資産と負債が大幅に増加し、財務諸表に与える影響も大きくなります。そのため、適切なシステム対応が不可欠です。
システム整備の必要性
新リース会計基準に対応するためには、以下のようなシステム整備が求められます。
- 会計システムの改修または新規導入:
リース取引を正確に計上するためには、専用の会計システムが必要です。これにより、リース資産の減価償却やリース負債の利息計算など、複雑な処理を自動化し、人的ミスを減少させることができます。 - 契約管理システムの導入:
リース契約の情報を一元管理するためのシステムが必要です。これにより、契約の更新や解約オプションの行使可能性を適切に評価し、リース期間の算定を正確に行うことができます。 - データベースの整備:
すべてのリース契約に関するデータを正確に収集し、管理するためのデータベースが必要です。特に、複数の契約が存在する場合や、契約内容が変更される場合には、最新の情報を常に把握することが求められます。
システム対応のメリット
システム対応を行うことで、企業は以下のようなメリットを享受できます。
- 効率的な業務運営:
自動化されたシステムにより、手作業での処理が減少し、業務の効率化が図れます。これにより、経理部門の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになります。 - 正確な財務報告:
システムによる正確なデータ管理が実現することで、財務報告の信頼性が向上します。これにより、投資家や取引先に対する透明性が高まり、企業の信頼性が向上します。 - 迅速な対応:
新基準に基づく会計処理が迅速に行えるため、決算業務のスピードが向上します。これにより、四半期決算や年次決算における業務負担が軽減され、タイムリーな情報提供が可能になります。
新リース会計基準対応のリース資産管理システム導入に関する相談はこちらから!>>
税務・管理会計への影響と対応
新リース会計基準の適用は、会計処理だけでなく、税務や管理会計にも影響を及ぼす可能性があります。これらの分野での対応も、早期のうちに検討を始めることが重要です。
税務への影響
現時点では、新リース会計基準の適用に伴う税務上の取り扱いについて、明確な指針は示されていません。しかし、2025年度の税制改正において、何らかの法整備がなされることが期待されています。
税務上の主な検討ポイントとしては以下が挙げられます:
- 法人税:オペレーティング・リースのオンバランス化に伴う減価償却費や支払利息の税務上の取り扱い
- 消費税:リース取引に係る消費税の計算方法や申告時期への影響
- 固定資産税:使用権資産に対する固定資産税の課税の有無
これらの点について、今後の税制改正の動向を注視しつつ、必要に応じて税務当局や税理士との相談を行うことをお勧めします。
管理会計への影響
新リース会計基準の適用は、企業の管理会計にも大きな影響を与える可能性があります。主な検討ポイントとしては以下が挙げられます。
- 業績評価指標の見直し:
EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却前利益)などの指標が変化する可能性があるため、業績評価の基準を再検討する必要があります。 - 予算管理の変更:
リース取引のオンバランス化に伴い、予算の立て方や管理方法の変更が必要になる可能性があります。 - 投資判断基準の見直し:
リースとその他の資金調達方法との比較方法が変わる可能性があるため、設備投資の判断基準を見直す必要があるかもしれません。 - セグメント情報への影響:
セグメント別の資産や負債、利益の数値が変化する可能性があるため、セグメント情報の作成方法や分析方法の見直しが必要になるかもしれません。
これらの点について、早期のうちに検討を始め、必要に応じて管理会計の仕組みを見直すことが重要です。
新リース会計基準に対応したシステム
新リース会計基準の早期適用に向けて、主要なシステムベンダーが対応を進めています。以下に、各社の対応状況をまとめます。(2024年11月現在 当社が各社ウェブサイトより調べ 詳細は各社のHPをご確認ください)
OBCの『固定資産奉行V ERPクラウド』
OBCは2025年4月から、新リース会計基準に対応する機能を『固定資産奉行V ERPクラウド』のシステム標準で提供開始することを発表しています。主な機能には以下が含まれます:
- 財務諸表への影響額試算
- 適用初年度における遡及計算への対応
- 使用権資産・リース負債の計算対応
- リース負債の見直し
これらの機能により、新基準への対応に伴う業務負荷を大幅に軽減することが期待できます。
ワークスアプリケーションズの対応
ワークスアプリケーションズは、2つのソリューションを提供しています:
1.固定資産管理システム「HUE Asset」:
- 2024年10月初旬に新リース会計基準に準拠した機能をリリース
- リース期間測定、前払リース料、当初直接コスト、インセンティブ等の主要な変更点に対応
- 入力から自動計算・照会出力までの機能を幅広くサポート
2.新リース会計基準対応SaaS「HUEリース会計」:
- 2025年春に提供予定
- 契約情報に基づく償却計算や利息計算
- 再見積や減損処理
- 仕訳や注記に必要な増減情報の自動集計
- 別表十六の元情報の作成
高い機能と応用性を兼ね備えたソリューションを提供しています。SaaS版のリリースも発表されていますが、主にエンタープライズ企業の利用が見込まれています。
multibookのIFRS16号リース資産管理ソリューション
multibookは、IFRS16号リース資産管理に日本で初めてSaaS対応したクラウドERPソリューションです。以下の特徴を持っています:
- 短期導入:
最短2週間、通常1ヶ月での導入が可能で、Excelによる管理からの脱却を迅速に実現します。 - グローバル対応:
12ヶ国語に対応し、多通貨管理が可能なため、グローバル企業での一元管理に適しています。 - 複数基準対応:
ローカル基準とIFRS基準の両方に対応し、連結修正仕訳情報や連結注記情報を自動出力します。 - 自動計算機能:
- 少額・短期・資産計上の自動判定
- 使用権資産・リース負債の当初計上額の自動計算
- 毎月の減価償却費、リース負債返済額、支払利息額の自動算出
- 業務効率化:
連結修正仕訳や注記作成の作業時間を大幅に削減します。例えば、ある企業では40時間から20時間に短縮されました。 - 低コスト:
少ないリース資産数でも利用可能な低価格プランがあります。 - 監査対応:
標準化された処理により、監査法人の理解を促進し、監査プロセスを効率化します。 - 柔軟な対応:
前払や再測定など煩雑な計算もシステム化し、業務を効率化します。
multibookは、IFRS16号対応に伴う複雑な会計処理や増加する業務負担を効果的に軽減し、グローバル企業の新リース会計基準に対応した資産管理を強力にサポートします。
新リース会計基準に完全対応!multibookリース資産管理システムのサービス紹介資料をメールで受け取る>>
これらのソリューションにより、企業は新リース会計基準への対応を効率的に進めることができます。
まとめ
新リース会計基準への対応には、適切なシステムの導入が不可欠です。OBC、multibook、ワークスアプリケーションズなどのシステムベンダーが提供するソリューションを上手に活用することで、複雑化する会計処理や増加する業務負担に効果的に対処できます。企業は自社の状況に合わせて最適なソリューションを選択し、早期に準備を進めることが重要です。
早期適用に際してシステムの選定は必ず必要になります。選定する際は、特にIFRS16号リースのシステム提供の経験あるシステムから優先的に検討を行い、メリットとデメリットを十分に検討した上で判断することが求められます。
なお、新リース会計基準に関する法令や税務上の取り扱いや各企業の情報は、今後変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。